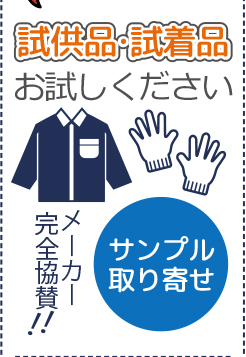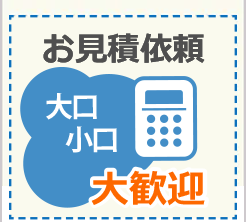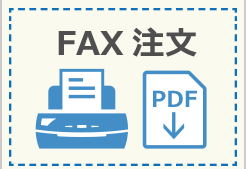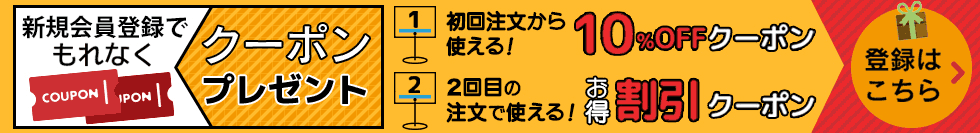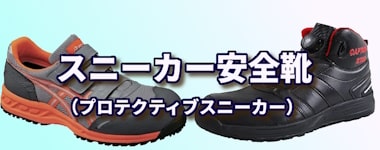はじめに
工場や建設現場では、重量物の落下や資材の踏み抜き、機械への巻き込みなど、足元には常に危険が潜んでいます。このような環境で作業者の安全を確保するために不可欠なのが「安全靴」です。労働安全衛生規則によって、事業者は作業内容に応じて適切な履物を労働者に着用させることが義務付けられており、労働者もその指示に従う必要があります。
建設現場や工場等で働く作業者の方々が安全靴を選ぶ目安として、JIS規格の安全靴に関する基礎知識から、他の規格との違い、現場に最適な一足を見つけるための選び方、そして安全性を維持するための買い替え時期のサインまでを詳しく解説し、皆様がご自身の足を守る最適な安全靴を選ぶ手助けとなる情報をご紹介します。
JIS規格安全靴の総合売れ筋ランキング
![[シモン] 安全靴 7511 黒](/upload/save_image/60406_01.jpg)
- 人気No.1
- [シモン] 安全靴 7511 黒
サイズ:23.5〜28.0cm
質量:約400g(26.0cm片足)- ¥8,322
- 購入ページ »
![[ジーベック] 安全靴(JIS規格)長編上 85023](/upload/save_image/60308_01.jpg)
- 人気No.2
- [ジーベック] 安全靴(JIS規格)長編上 85023
サイズ:24.0〜29.0cm
質量:約550g(26.0cm片足)- ¥11,609
- 購入ページ »

- 人気No.3
- KF1055 野口ゴム工業 安全靴 スタンダードタイプ ブラック
サイズ:23.5〜28.0cm
質量:約450g(25.5cm片足)- ¥5,196
- 購入ページ »
JIS規格安全靴の基礎知識
JIS規格(JIS T8101等)とは
JIS(Japanese Industrial Standards:日本産業規格)とは、日本の工業製品に関する国家規格です。安全靴においては「JIS T 8101(安全靴)」が主要な規格であり、「主として着用者のつま先を先芯によって防護し、滑り止めを備える靴」と定義されています。JIS規格に適合した安全靴は、厳しい検査をクリアしているため、その安全性が国によって保障されていると言えます。
JIS規格の認定基準・試験内容
JIS規格の安全靴は、以下の基本性能試験に合格する必要があります。
- ・耐衝撃性能
- 重量物がつま先に落下した際の衝撃から足を守る性能。特定の高さから20kgのストライカーを落とし、先芯がつぶれずに規定以上の隙間を確保できるかが評価されます。
- ・耐圧迫性能
- つま先に重量物が乗った際の荷重から足を守る性能。規定の圧迫力をかけた際に先芯がつぶれずに規定以上の隙間を確保できるかが評価されます。
- ・表底のはく離抵抗
- 靴底と甲被の接着強度。強い力で引っ張っても剥がれない強度が求められます。
これらの基本性能に加え、作業環境に応じた多様な「付加的性能」の項目も設けられています。例えば、耐踏抜き性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、足甲プロテクタの耐衝撃性、耐滑性、耐水性、電気絶縁特性、耐熱伝導性などがあり、製品にはこれらの性能を示す記号が付与されます。
JIS規格では、主に以下の4種類の作業区分があります。
| 種類 | 記号 | 耐衝撃性能(※1) | 耐圧迫性能(※2) |
|---|---|---|---|
| 超重作業 | U種 | 200J に耐える | 15kN に耐える |
| 重作業 | H種 | 100J に耐える | 15kN に耐える |
| 普通作業 | S種 | 70J に耐える | 10kN に耐える |
| 軽作業 | L種 | 30J に耐える | 4.5kN に耐える |
(※1)約20kg(ビール瓶1ケース程度の重さ)の鋼鉄の試験片を落として計測。種類ごとに落とす高さが変わります。
(※2)1kNは約100kg(0.1t)の重さを表します。10kNで約1トン、15kNで約1.5トンの重量になります。
日本では普通作業用(S種)が最も広く普及しており、多くの現場で利用されています。
重作業用(H種)JIS規格安全靴の売れ筋ランキング
![[ジーベック] 安全靴(JIS規格)短靴 85025](/upload/save_image/60304_01.jpg)
- 人気No.1
- [ジーベック] 安全靴(JIS規格)短靴 85025
サイズ:24.0〜29.0cm
質量:約530g(26.0cm片足)- ¥6,362
- 購入ページ »
![[ジーベック] 安全靴(JIS規格)長編上 85027](/upload/save_image/60305_01.jpg)
- 人気No.2
- [ジーベック] 安全靴(JIS規格)長編上 85027
サイズ:24.0〜29.0cm
質量:約650g(26.0cm片足)- ¥9,832
- 購入ページ »
![[ジーベック] 安全靴(JIS規格)半長靴 85028](/upload/save_image/60306_01.jpg)
- 人気No.3
- [ジーベック] 安全靴(JIS規格)半長靴 85028
サイズ:24.0〜29.0cm
質量:約660g(26.0cm片足)- ¥9,832
- 購入ページ »
普通作業用(S種)JIS規格安全靴の売れ筋ランキング
![[シモン] 安全靴 7511 黒](/upload/save_image/60406_01.jpg)
- 人気No.1
- [シモン] 安全靴 7511 黒
サイズ:23.5〜28.0cm
質量:約400g(26.0cm片足)- ¥8,322
- 購入ページ »
![[ジーベック] 安全靴(JIS規格)中編上 85022](/upload/save_image/60307_01.jpg)
- 人気No.2
- [ジーベック] 安全靴(JIS規格)中編上 85022
サイズ:24.0〜29.0cm
質量:約450g(26.0cm片足)- ¥8,820
- 購入ページ »
![[日進ゴム] 安全靴Hyper V #9000](/upload/save_image/66492_01.jpg)
- 人気No.3
- [日進ゴム] 安全靴Hyper V #9000
サイズ:24.5〜29.0cm
質量:約530g(26.0cm片足)- ¥10,890
- 購入ページ »
JISマークの見分け方
JIS規格に合格した安全靴には、靴底や中敷き、商品の箱やタグなどにJISマークが必ず表示されています。このマークと「JIS T-8101 革製S種(普通作業用)合格品」といった記載を確認することで、JIS規格を満たしているかを判断できます。マークのない先芯入り靴は、公的な認定を受けていないため、その性能には注意が必要です。
JIS規格の新旧・国際規格との違い
JIS T 8101規格は、2020年3月に改定されました。主な変更点として、「超重作業用(U種)」の追加、付加的性能の項目が4項目から12項目への増加、耐滑性の細分化、交換可能な中敷の規定などが挙げられます。旧規格の製品も引き続き使用可能であり、ミドリ安全などのメーカーでは旧版合格品も新版と同等以上の性能認定を受ける見込みとされています。
このJIS規格は、国際規格であるISO 20345およびISO 20346を基に、日本の安全靴の使用用途や管理方法に合わせて技術的変更を加えて作成されています。
JSAA規格・プロテクティブスニーカー等 他規格との違い
JSAA規格の特徴と種類
JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)規格は、JIS規格の安全靴を必要としない作業現場での足元を守るために制定された規格です。つま先に金属または硬質樹脂の先芯を装備し、一定の安全性能と耐久性の基準を満たしたスニーカータイプの作業靴を「プロテクティブスニーカー(プロスニーカー®)」、長靴タイプを「プロテクティブブーツ(プロブーツ®)」と呼び、JSAAが認定しています。
JSAA規格は、以下の2種類の作業区分に分かれています。
・普通作業用(A種): JIS規格のS種(普通作業用)に相当する性能を持つ。貨物運送・運搬業、一般事務作業、清掃作業など、通常作業に適しています。
・軽作業用(B種): JIS規格のL種(軽作業用)に相当する性能を持つ。軽量物を扱う作業や比較的良好な職場環境での軽作業に適しています。
JSAA規格のプロテクティブスニーカーは、革製・ゴム製のほか、人工皮革製、合成皮革製、編物製、プラスチック製といった多様な素材の使用が認められている点が特徴です。
JSAA規格スニーカー安全靴の売れ筋ランキング
![[ジーベック] セフティシューズ85147](/upload/save_image/19138_01.jpg)
- 人気No.1
- [ジーベック] セフティシューズ85147
サイズ:22.0〜30.0cm
質量:約390g(26.0cm片足)
カラー:4色
JSAA A種認定品- ¥4,150
- 購入ページ »

- 人気No.2
- AZ-51658 アイトス TULTEX セーフティシューズ(耐油・耐滑・静電)
サイズ:22.0〜30.0cm
質量:約330g(26.0cm片足)
カラー:2色
JSAA B種認定品- ¥4,612
- 購入ページ »
![[丸五] 安全靴マンダムニットSOC#201](/upload/save_image/18477_01.jpg)
- 人気No.3
- [丸五] 安全靴マンダムニットSOC#201
サイズ:25.0〜28.0cm
質量:約380g(26.5cm片足)
カラー:3色
JSAA A種認定品- ¥5,170
- 購入ページ »
スニーカー安全靴関連リンク
JIS規格との主な違い
JIS規格とJSAA規格の主な違いは以下の点です。特に危険度の高い重作業にはJIS規格品が推奨されます。
| 項目 | JIS規格(安全靴) | JSAA規格(プロテクティブスニーカー) |
|---|---|---|
| 認定団体 | 国家規格(日本産業標準調査会) | 公益社団法人(日本保安用品協会) |
| 甲被(アッパー)素材の制限 | 「牛革製」または「総ゴム製」に限定 | 「人工皮革」や「合成皮革」、「メッシュ素材」など、より多様な素材が使用可能 |
| 耐久性とデザイン | 素材の制限により高い耐久性と安全性を誇りますが、デザインの選択肢は限られます。 | 一定の安全性を持ちつつ、素材の自由度が高いため、軽量でデザインが豊富、履き心地が良い製品が多いです。 |
| 想定される作業の強度 | 超重作業から軽作業まで幅広い強度に対応 | 普通作業用(A種)と軽作業用(B種)が中心 |
現場ごとの使い分けポイント
・JIS規格安全靴: JIS規格の着用が義務付けられている現場や、重量物の落下・圧迫など足元への危険性が高い現場(鉱山、鉄鋼、造船、建設現場など)に適しています。特に高強度を求める場合は、H種やU種を検討しましょう。
・JSAA規格プロテクティブスニーカー: JIS規格ほどの強度・耐久性は不要だが、一定の安全性が求められる現場(物流・倉庫作業、工場内の軽作業、サービス業など)に適しています。軽量性やデザイン性、履き心地を重視したい場合に選択肢となります。
安全靴の選び方 ~現場に最適な一足を見つける基準~
安全靴を選ぶ際は、作業内容や環境に合ったものを選ぶことが重要です。以下のポイントを参考に、最適な一足を見つけましょう。
つま先保護・耐衝撃性
安全靴の最も重要な機能の一つが、先芯によるつま先保護です。
・鋼製先芯: 強度が高く、重量物の落下や圧迫に対する保護性能に優れています。建設現場や重量物を扱う工場など、高い安全性が求められる現場に適しています。
・樹脂先芯: 鋼製に比べて軽量で、金属探知機に反応しないため、セキュリティチェックのある場所や動きやすさを重視する現場に適しています。冷えにくいという特徴もあります。
作業区分(U種、H種、S種、L種、A種、B種)を確認し、想定される危険度に応じた耐衝撃性・耐圧迫性を持つものを選びましょう。
耐久性・素材の違い
安全靴の耐久性は甲被(アッパー)と靴底の素材に大きく左右されます。
- 甲被の素材
- 本革: 熱や摩擦に強く、耐久性が高いです。溶接現場や建築現場に適しています。
- 合成皮革: 本革に比べて耐熱性や耐久性は劣りますが、軽量で安価、デザインも豊富です。工場、倉庫、運送業など幅広い場面で利用されます。
- メッシュ素材(ナイロンなど): 軽量で通気性が良く、蒸れにくいのが特徴です。軽作業や夏場の作業に適していますが、水気には注意が必要です。
- 総ゴム・総高分子: 耐水性が高く、水気の多い現場や長靴タイプに用いられます。
- 靴底の素材
- 天然ゴム: 弾性や耐摩擦性、耐寒性に優れます。熱や油を使わない現場で幅広く活用できます。
- 合成ゴム: 耐熱性や耐油性に優れ、様々な環境に対応可能です。
- ポリウレタン: 軽量でクッション性が高く、足への負担を軽減します。ただし、熱に弱く、長期間の保管で加水分解による劣化が進むことがあります。
履き心地・重量・デザイン
長時間の作業では履き心地の良さが疲労軽減に直結します。
- 重量
- 軽量な安全靴は、動き回る作業が多い場合に足への負担を軽減します。樹脂先芯やEVAミッドソールを採用した製品が軽量性に優れます。
- クッション性
- かかと部の衝撃エネルギー吸収性(JIS規格、JSAA規格も対応)が高い製品は、歩行時の衝撃を和らげ、足の疲労を軽減します。インソールで調整することも可能です。
- 通気性
- メッシュ素材やエアサイクルシステムなどを採用した通気性の良い安全靴は、足の蒸れや臭いを軽減し、快適な作業環境を保ちます。
- デザイン
- ASICS、PUMA、ミズノなどスポーツ用品メーカーの参入により、最近ではスポーツシューズのようなおしゃれなデザインの安全靴も増えています。JSAA規格品に多く見られ、通勤時にも違和感なく履けるものもあります。
形状(ブーツ・短靴・スニーカータイプなど)の選び方
安全靴には作業内容に適した様々な形状があります。
- 短靴(ローカット)
- 着脱しやすく、一般的な作業全般に適しています。
- 中編上靴(ハイカット)
- 足首を覆い、溶接火花や砂、切子などの侵入を防ぎます。足首の保護にも優れ、運搬作業にも適しています。
- 長編上靴(ブーツタイプ)
- 脛までを覆い、ズボンの裾を収納できるため、建築・土木作業や高所作業に適しています。
- 半長靴
- 紐がなく、ゴム長靴のように着脱しやすいのが特徴です。着脱の機会が多い現場に向いています。
- スニーカータイプ
- 軽量でデザイン性が高く、軽作業や動きやすさを重視する現場で人気です。
付加性能(防水・静電・耐油・耐熱・クッション性等)
特定の作業環境では、基本性能に加えて特別な付加性能が求められます。
- 防水性(JIS規格W)
- 水気の多い現場や屋外作業で足の濡れを防ぎます。ゴアテックスなどの素材を使用した製品もあります。
- 静電・帯電防止性(JIS T 8103、JSAA規格も対応)
- 人体に帯電した静電気を放電し、爆発・火災のリスクや電子機器の破損を防ぎます。ガソリンスタンドや精密機器工場などで必須です。
- 耐油性(JIS規格BO/UO)
- 油脂類が付着しても劣化しにくい性能です。石油工場や食品加工工場など、油を扱う現場で重要です。耐油性は「滑りにくさ」とは異なるため、滑りやすい環境では「耐滑性」も兼ね備えたものを選びましょう。
- 耐熱性(JIS規格H/HI)
- 高温の床や熱源に近い場所での作業で、足への熱伝導を防ぎます。溶接作業や炉前作業などに適しています。
- 耐滑性(JIS規格F1/F2、JSAA規格も対応)
- 水や油で滑りやすい床面での転倒を防ぎます。靴底の凹凸の形状や素材が重要です。
- 耐踏抜き性(JIS規格P、JSAA規格も対応)
- 釘やガラスなどの鋭利な物を踏み抜く危険から足裏を守ります。解体工事や産廃処理場などで役立ちます。
- 足甲プロテクターの耐衝撃性(JIS規格M)
- 先芯でカバーできない足の甲部分を、落下物の衝撃から保護する機能です。
JIS T8103 静電気帯電防止仕様の安全靴の総合売れ筋ランキング
![[シモン] 静電安全靴 7511 黒](/upload/save_image/60411_01.jpg)
- 人気No.1
- [シモン] 静電安全靴 7511 黒
サイズ:23.5〜28.0cm
質量:約400g(26.0cm片足)- ¥8,732
- 購入ページ »
![[シモン] 静電安全靴 白 7517](/upload/save_image/17362_01.jpg)
- 人気No.2
- [シモン] 静電安全靴 白 7517
サイズ:23.5〜28.0cm
質量:約420g(26.0cm片足)- ¥10,746
- 購入ページ »
![[シモン] 静電安全靴 8818N 紺](/upload/save_image/60414_01.jpg)
- 人気No.3
- [シモン] 静電安全靴 8818N 紺
サイズ:23.5〜28.0cm
質量:約405g(26.0cm片足)- ¥8,472
- 購入ページ »
安全靴の交換・買い替え基準
安全靴は消耗品であり、使用頻度や環境によって劣化します。安全性を保つためには、適切なタイミングで買い替えることが重要です。
買い替えサインのチェックポイント
独立行政法人 労働安全衛生総合研究所が定める「安全靴・作業靴技術指針」では、以下の状態になったら交換・廃棄の目安とされています。
- ・甲被が破れ、着脱や歩行に支障をきたす、または先芯が露出している
- ・甲被と靴底の間に破れ目ができ、足が前へ滑る
- ・靴底にひび割れ・剥がれがある
- ・踏み付け部の滑り止めが摩耗し、凹凸の差が2mm以下になっている
- ・踵部分が大きく摩耗している
- ・つま先に強い衝撃を受け、先芯が破損または変形している(外見上問題がなくても、内部破損の可能性を考慮)
- ・はとめ、ボタンなどが脱落し、修理不能なもの
- ・かかとの腰革がつぶれたり、折れ曲がったりしたもの
- ・臭いがひどく、対策しても改善しない場合
安全靴の寿命は、おおよそ3,000円の靴で3ヶ月、12,000円の靴で12ヶ月という目安もありますが、使用頻度や環境、個人の歩き方の癖などによって大きく変動します。上記のチェックポイントに一つでも該当する場合は、速やかに交換を検討しましょう。
劣化・損傷箇所の具体例
- ・甲被の破れ: 特に指先、指の付け根、かかと部分は脱ぎ履きや擦れによって破れやすい箇所です。先芯が露出すると、先芯がずれて保護性能が低下する恐れがあります。
- ・甲被と靴底の間に破れ目ができ、足が前へ滑る
- ・靴底の剥がれ・ひび割れ・摩耗: 靴底が剥がれると歩行中に転倒の危険が高まります。発泡ポリウレタン製の靴底は加水分解によりひび割れや剥がれが生じやすいため、長期間使用していない場合や保管状況が悪い場合は特に注意が必要です。靴底の溝がなくなると滑りやすくなり、グリップ力が低下します。
- ・先芯の損傷: 強い衝撃や圧迫を受けた場合、外観に変形がなくても先芯の強度が低下している可能性があります。一度大きな衝撃を受けた安全靴は、見た目には問題なくとも内部が損傷している恐れがあるため、廃棄することが推奨されます。
安全靴を長持ちさせるケア方法
安全靴を長く安全に使用するためには、日頃のケアも大切です。
- ・定期的な清掃: 泥や汚れは素材の劣化を早める原因となります。使用後は汚れを拭き取りましょう。
- ・乾燥: 雨などで濡れた場合は、風通しの良い日陰でしっかりと乾燥させましょう。高温多湿での保管は劣化を早めます。ビニール袋に入れての保管は避け、靴箱に保管する場合は穴を開けて通気性を確保することが望ましいです。
- ・複数足での履き回し: 毎日同じ靴を履くと劣化が早まります。複数足用意し、ローテーションで履き回すことで靴の寿命を延ばせます。
- ・インソールの交換: インソールは消耗品であり、汚れやヘタリによってクッション性や衛生状態が悪化します。定期的に交換することで、履き心地を改善し、臭い対策にもなります。ただし、JIS規格品では中敷きを交換する場合、同一メーカーの同等品に限定するよう規定されているため注意が必要です。
まとめ
JIS規格安全靴を正しく選ぶために
工場や建設現場での安全な作業には、適切な安全靴の着用が不可欠です。JIS規格の安全靴は、国が定めた厳しい基準をクリアした高い安全性を持つ製品であり、特に危険度の高い現場ではその着用が義務付けられています。JSAA規格のプロテクティブスニーカーは、JIS規格に次ぐ安全性を持ちながら、軽量性やデザイン性に優れており、軽作業や動きやすさを重視する現場に適しています。
ご自身の作業内容や環境を正確に把握し、必要な保護性能(耐衝撃性、耐圧迫性、耐滑性、耐踏抜き性、静電性、耐油性、耐熱性など)を備えた安全靴を選びましょう。また、足の形状に合ったサイズ選びや、履き心地、通気性なども快適な作業には欠かせません。
適切な着用と管理で安全性アップ
安全靴は、購入時だけでなく、日々の適切な着用と管理によってその性能を最大限に発揮します。定期的に安全靴の状態をチェックし、甲被の破れ、靴底の剥がれや摩耗、先芯の損傷といった買い替えサインを見逃さないようにしましょう。
関連ページのご案内
JIS規格安全靴の関連特集
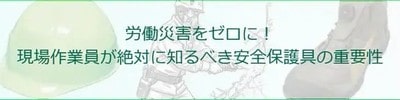
- 労働災害をゼロに! 現場作業員が絶対に知るべき安全保護具の重要性
現場で労災の危険から作業員を守る安全保護具。建設業、運輸業をはじめ労働力不足が深刻な問題になっている事業者において、社員のケガや事故は時に会社の存続にも関わる重大リスクとなります。正しい知識で安全保護具を揃え、作業者の安全を守る事は、会社の持続的な事業展開にも繋がります。
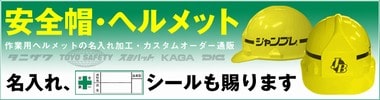
- 作業用ヘルメットの名入れ加工・カスタムオーダー通販
危険を伴う作業現場の必需品、作業用ヘルメット(安全ヘルメット)。メーカーや作業シーンなど、様々な切り口からおすすめのヘルメットをご紹介します。
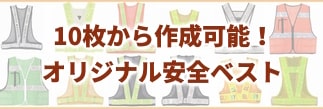
- オリジナル安全ベスト(名入れ安全ベスト)制作承ります
安全ベストの名前入れ・社名入れはお任せください! 最少10枚から名入れ対応。パトロールベストやタスキ型など各種デザインの名入れベストを作れます。フルカラー名入れにも対応。
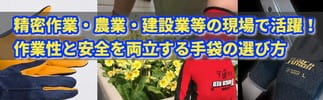
- 精密作業・農業・建設業等の現場で活躍! 作業性と安全を両立する手袋の選び方
様々な現場で働く作業者の方が、安全で効率よく作業するために最適な手袋をご紹介。軍手やゴム手袋から耐切創手袋まで多様な種類の手袋を分類・ご紹介します。
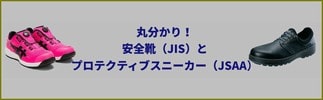
- 安全もオシャレも叶える安全靴とプロテクティブスニーカー
働く人の足を守るワークシューズには、安全靴とプロテクティブスニーカーの2つの規格が存在します。普段は意識せずどちらも安全靴と呼ばれる事が多い両者の特徴や違いから、お手入れ方法まで丁寧に解説します。

 はじめての方へ
はじめての方へ 5,500円(税込)以上のご注文で送料無料! カード決済対応
5,500円(税込)以上のご注文で送料無料! カード決済対応 【メルマガ会員限定】割引対象の予定カレンダー公開中!
【メルマガ会員限定】割引対象の予定カレンダー公開中!